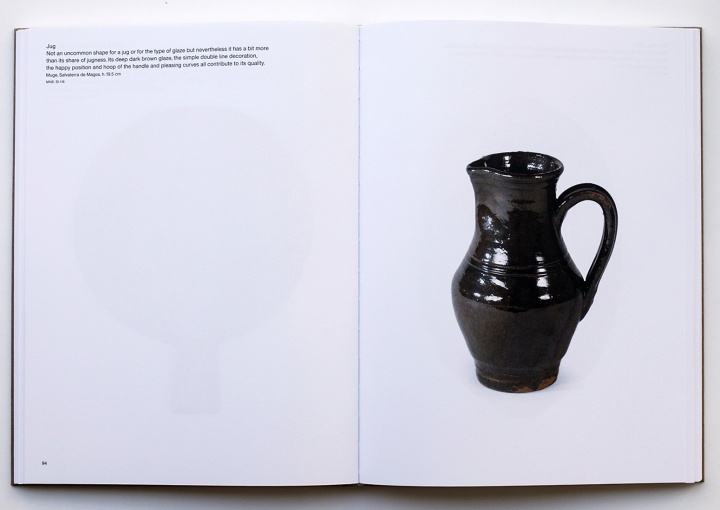そうした経緯もある展覧会では、「Riverbed(「川床」の意味)」という巨大なインスタレーション作品があらわれました。会場に足を踏み入れると、見渡す限りに広がっているのは無骨な岩場。本来なら美術館の外側にある自然のランドスケープのようなものが、人間のつくりだした美術館の内部空間に突如現れています。この不測の事態に、来場者も最初は戸惑いを隠せません。
よくよく見ていくと、代わり映えのしないグレイッシュな景観のなかに、ステップがあり、溢れ出る水の音が聞こえ、人々が歩き回っていることがわかってきます。かぎりなく自然にも見えるけれど、光の質や湿度、大気のコンディションなどが明らかに違い、生命の気配もありません。すべてが明らかに人工的で、どこかこしらえたような趣があります。白い壁に覆われているという事実が、美術館のなかに現れたランドスケープであることを思い出させます。川の端から展覧会に入場した来館者は、川の流れに逆らうようにして上流に向かって歩いていきます。歩みを進めていくことこそが、この作品の核となり、意識は美術館の内部から外の世界へと拡張していきます。
本展を「ラディカル(先鋭的)」と評する見方が多いようですが、その斬新さやインパクトだけで語ってしまうのはごく表面的な理解にとどまってしまう恐れがあります。実のところ、この表現には美術館という施設における存在意義を問う、本質的な部分に鋭く切り込むような一面が秘められていました。世間一般に「美術館は現実からかけ離れている必要がある」という認識をしている方もいますが、エリアソンはこれには賛同しません。むしろ、「美術館に足を踏み入れた時には、現実をより深く見るためのひとつの方法とみなして作品と対峙するのがいい」と考えています。
実はこれらの岩、彼が拠点とするアイスランドのものが使われています。自身とも親和性の高い素材が起用され、自然のランドスケープという形になってあらわれた彼の芸術性と美術館という場所とが出逢い、この場所でしか成立しえない、言うなれば「サイトスペシフィック」な作品が生まれました。実際にエリアソンは、この作品を同じ方法で別の場所に創作するようなことはないと断言しています。本書に収録された会場風景写真は、オランダ出身の写真家であるイワン・バーン(1975年生まれ)が手がけました。レム・コールハース、ヘルツォーグ・ド・ムーロン、ザハ・ハディット、伊東豊雄、SANAAという錚々たる建築家の作品群と向き合ってきた経験で重ねた腕前を最大限に発揮し、会場に広がるランドスケープの圧倒的なスケール感を余すことなく撮り納めています。本書では見開きページに裁ち落としの状態で繰り返し展開することで、読者にまるで会場内を歩き廻るかのような疑似体験をもたらします。