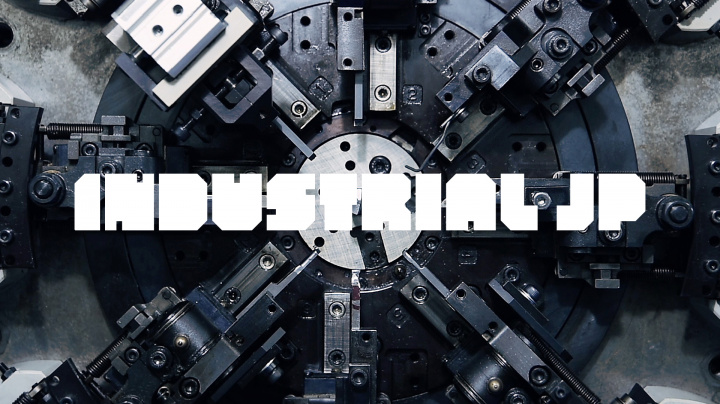Creator’s file
photograph by Chikashi Kasai
青野尚子・文
text by Naoko Aono

小さな声をすくい上げる、
ドキュメンタリー写真。
写真家、千賀健史はかつて物理の道に進もうとしていた。そしていまはドキュメンタリー写真に軸足を置いて活動している。物理とドキュメンタリーの共通点とはなんだろう?
「目に見えない新しい物理の法則や物質を見つけたいと思ったんです。誰も見ていないものをいち早く違うかたちで見たい。同時に、他者の生き方や考えにも興味がありました」
親しい人でも知らない人でも、表面だけ見ていたのではわからないことがある。たとえば千賀の写真集『サプレスド・ボイス』は彼が数年来通っているインドで出会った少年を追ったものだ。彼はインド北部のガヤという街で、貧しい人々のために開設されたフリースクールに通う生徒だったが、16歳の時に行方不明になってしまった。少年が見つかったのはガヤから1500㎞離れた南インドの洋服店。義務教育が終わった後、兄が連れ出していたのだ。少年は使い古した英語の教科書を大切に持ち歩いていた。勉学の夢を絶たれたが、兄の言うことは絶対だからしょうがない、と言う。
「街角の服屋さんで店番をしている男の子なんてありふれた光景だから、知らなければ通り過ぎてしまう。そこに至る事情や背景を知っているのと知らないのとでは、イメージの受け取り方が変わってくる。僕は写真に受け手の想像が入り込む余地や自由度があっていいと思っています」
そんな見えない糸を紡ぎ出すために千賀は写真集や展示にちょっとした仕掛けを施す。さりげなく被写体にポーズをとらせたり、登場する人物とは一見関係なさそうな写真や印刷物を入れたり。展示では壁に写真を貼る従来の展示方法の他、水を入れたアクリルの箱の下に写真を置いた。離れて見ると水の入ったただの水槽だけれど、のぞき込むと揺れる水底に写真が見える。
「ビジュアルによって物語を紡いでいく僕のやり方は、既存のジャーナリズムの手法とは少し違うと思います」
洋服店の店番の少年は16歳なので児童労働とはならない。法に反してはいないから、ともすればジャーナリズムの目には留まらない。千賀の写真はそんな、見過ごされてしまう声を丹念にすくい上げる。それは他者が抱える問題であっても、自らの身に起こることだってあるからだ。誰かの物語はあなたの物語になり得る普遍的な問題だ。千賀はそう考えているから、写真を撮り続けている。


1月にガーディアン・ガーデンで開かれた「ワン・ウォール」グランプリ受賞展の展示風景。
photo by Kenji Chiga

『サプレスド・ボイス』より、洋服店の店頭に立つ少年。千賀は2011年に初めて会ってから、ずっとこの少年を追っていた。
photo by Kenji Chiga