Pen本誌では毎号、作家・小川哲がエッセイ『はみだす大人の処世術』を寄稿。ここでは同連載で過去に掲載したものを公開したい。
“人の世は住みにくい”のはいつの時代も変わらない。日常の煩わしい場面で小川が実践している、一風変わった処世術を披露する。第28回のキーワードは「“性格がいい”とは?」。
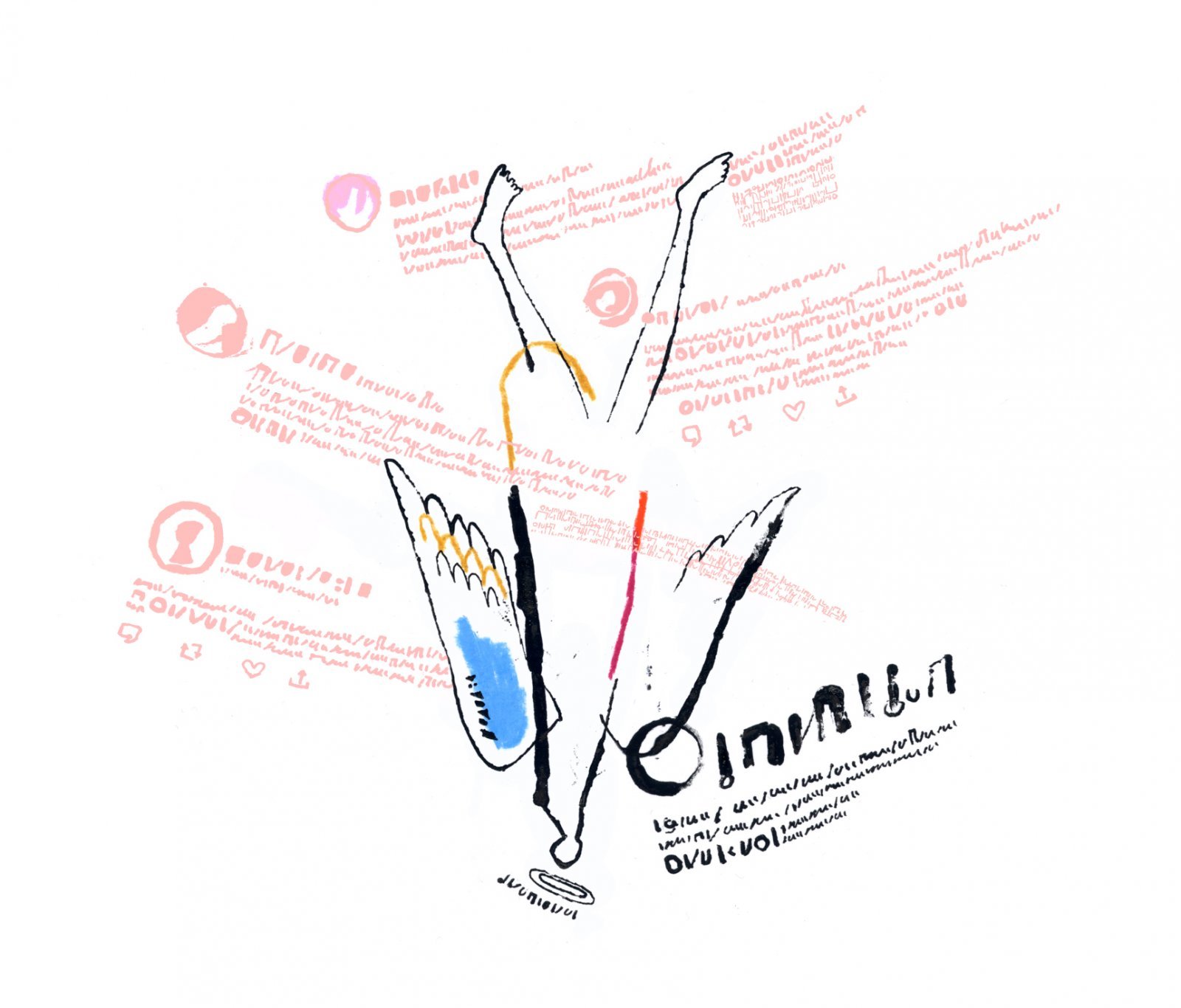
“性格がいい”ってなんだろう、とよく思う。たとえば僕は“性格が悪い”と自認しているのだが、かといって他人に怒ったりすることはないので、もしかしたら優しいと思われているかもしれない。とはいえ僕が他人に怒らないのは、広い心の持ち主だからではなくて、むしろとても心が狭いからだ。
僕は他人の人生にあまり興味がない。「ある程度の年齢になったら人間の性格はほとんど変わらない」とあきらめている。誰かに怒ると、怒った本人は非常に疲れるし、多くの場合は嫌われるということを知っている。だから怒らないのだが、これは“性格がいい”のだろうか。誰かに怒られなければ、失礼なことをしたり、間違ったことをしたりしている人は、同じことを繰り返してしまうかもしれない。本当は怒ったり叱ったりしたほうが、長期的に見て役に立つこともあるだろう。
たとえばあまり仕事のできない知人が、「独立して起業したい」と夢を語っていたりする。“性格がいい人”はどういう言葉を発するだろうか――「お前ならできるよ」と応援するかもしれないし、「そんな甘い考えで起業したら失敗するぞ」と釘を刺すかもしれない。どちらにせよ、根底にあるのはきっと「相手の人生について真剣に考えている」という前提だろう。ちなみに僕は「いいね」などと適当にやり過ごすと思う。もし「お前はどう思ってるか正直に教えて」と言われたりしたら、「無理だと思う」などと口にするかもしれないが、自分から言ったりはしない。「難しそうだなあ」と感じつつ、「お前ならできるよ」などとお世辞を口にするのも嫌なので、「いいね」と無難な対応をしながら、「でも事業に行き詰まってもお金は貸さないでおこう」などと心の中で勝手にルールをつくっている。
僕の経験では、SNSでよく炎上している人に実際に会うと、“性格がいい”ことが多い。彼らは“性格がいい”からこそ炎上しているのだろう。“性格がいい人”は、自分の思いをまっすぐ言葉にする。そのせいで意地の悪い人に深読みされたり、無自覚なまま誰かを傷つけてしまったり、誤解や憶測を生んでしまったりする。
逆に、SNSを上手に使っている人が“性格が悪い”こともある。性格が悪いからこそ、「こういうことを言うと意地悪な解釈をされてしまうかもしれない」とか、「こういう屁理屈を言われるかもしれない」とか、脳内でさまざまなケーススタディができるので、慎重に言葉を選ぶ。本心のまま言葉にすれば誰かからイチャモンをつけられると知っているので、なるべく無難な内容を投稿する。
僕が現役のSNSの使い方を教える講師のような仕事をするとしたら、ある投稿(内容はなんでもいい)に対して、できる限り多くのクソリプ(クソみたいな返事)を考えてもらう、という授業をすると思う。“性格がいい人”は、あまり多くの例を出せないはずだ。自分で投稿する前に、あらかじめ自分の脳内でクソリプの例を出せない故に炎上してしまうのだ。もしかしたら“性格がいい”と思われるためには、“性格の悪さ”が必要だ、とすら言えるかもしれない。“性格がいい”という言葉は難しい。自分が感じる優しさは、むしろ冷たさに由来するものかもしれないし、厳しさは愛から生まれているのかもしれない。性格がひねくれているからこそ、相手の考えを想像することができる、という側面もあるだろう。現代では、誰かに意地悪なことを言われたら「この世にはそういう発想もあるのか」と勉強するくらいがちょうどいいのかもしれない。
小川 哲
1986年、千葉県生まれ。2015年に『ユートロニカのこちら側』(早川書房)でデビューした。『ゲームの王国』(早川書房)が18年に第38回日本SF大賞と第31回山本周五郎賞受賞。23年1月に『地図と拳』(集英社)で第168回直木賞受賞。近著に『スメラミシング』(河出書房新社)がある。※この記事はPen 2025年4月号より再編集した記事です。