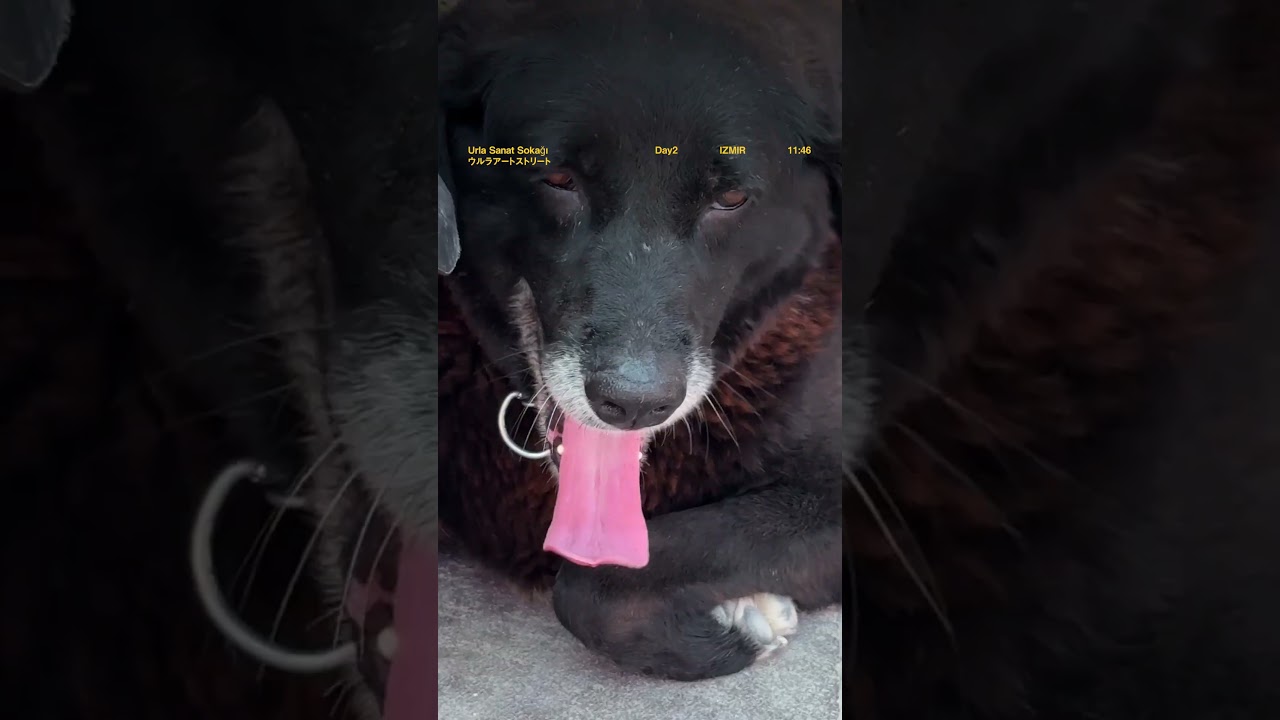
Pen Onlineでは、昨年に建国100周年を迎えたトルコ共和国の西海岸エリアを中心に、エーゲ海沿岸の各都市を巡る旅行記を連載中。全6回を予定するシリーズ第二弾の2日目は、イスタンブールから飛行機で約1時間南下して、イスタンブール、アンカラに次ぐ第三の都市イズミルへと移動した。
イズミルのアドナン・メンデレス空港から車を西へと走らせること約50分。穏やかな漁師街で、ワインやアーティチョークの原産地として知られるほか、オリーブオイル発祥の地とも言われるウルラに到着した。石畳が敷かれた「ウルラアートストリート」と呼ばれる中心地には、レンガ作りの古い街並みがあり、カフェ、レストラン、雑貨屋、食料品店、ベーカリー、床屋など、こぢんまりとした店が立ち並ぶ。こういった小さな街に訪れたなら、外国人観光客の多い大都会では見られないような、ローカルのリアルなライフスタイルを覗いてみたい。
この日はまだ午前中だったこともあり、地元の人が通う食料品店でいろんな種類のチーズやパンや新鮮な魚介類を見たり、アンティークショップでトルコの古い雑貨を見たりしながら、ゆっくりと散歩を楽しんだ。
---fadeinPager---



ローカルのライフスタイルを体験する際に外せないのが、独自のスタイルで愉しむトルココーヒー。 実はトルコのコーヒー文化にはかなりの歴史があって、焙煎した豆から抽出する飲み方の元祖として知られており、イスタンブールにはヨーロッパにカフェが登場する一世紀も早い1557年に、世界で最初のカフェが誕生したと言われている。深煎りのコーヒー豆を粉状に挽き、水からじっくり煮出したものを濾過せずに飲むトルココーヒーは、粉が沈澱するのを待ってから飲むのが正しい作法。小さなカップで飲むことからもわかる通り苦味が強く、エスプレッソのように砂糖を入れて飲むのが正解だ。トルココーヒーを飲み終わったら、カップに残された粉で占いもできる。願いを込めた後にソーサーの上にカップをひっくり返した状態で乗せ、しばらく待ってから元に戻すと、カップの中の粉がなにかのかたちに見えてくるはずだ。カップの下部は過去を、上部は未来を表すとされており、魚に見えたら金運、牡牛に見えたら仕事運、ハートに見えたら恋愛運といった具合に、自分の運勢を占うことができる。
トルコではチャイと呼ばれる紅茶も日常的に親しまれており、どんなスタイルの飲食店でも、一日中時間を問わず、いつでも気軽に楽しまれている。 トルコの家庭では、2段式のヤカン「チャイダンルック」で一日中チャイを沸かしているそうだ。トルコのチャイは、20分ほど弱火で煮出した濃い紅茶を小さなグラスに注ぎ、そこにお湯を注いで好みの濃さに調整してから飲む。
---fadeinPager---

ウルラアートストリートを歩いていたら、店の前にテーブルを広げ、オリーブの木を使った雑貨などを販売している可愛いショップを発見。ステーキ、チーズ、シャルキュトリなどをかっこよく盛り付けるのにぴったりなオリーブのカッティングボードは、日本で購入すると結構な高級品だが、オリーブの名産地として知られるウルラでは、比較的安価に手にいれることができる。他にもサラダボール、取り分け用のフォークやスプーン、マグカップなども豊富に揃い、あれも、これもと、ついついまとめ買いしてしまっても、レジで金額に驚く心配もないだろう。

ランチに訪れたのは、「ミシュランガイド イスタンブル、イズミル、ボドルム版 2024」で1つ星を獲得したオドゥ ウルラ(OD Urla)。2020年にオープンしたこのレストランでは、地産地消にこだわったガストロノミーが提供されている。敷地内では150種以上の野菜やハーブに加え、20種以上のオリーブが栽培されており、メニューには自家製のオリーブオイルも豊富にオンリストされている。中でも特に珍しいのが、ウルラのローカル品種であるフルマ・オリーブ。通常オリーブの実は生では渋くて食べられないが、このフルマ・オリーブの実は樹上で甘くなる非常に珍しい品種で、収穫してそのまま食べられる。フレッシュな食材と共にウルラのワインを愉しむ贅沢なランチは、トルコ料理のイメージをガラリと刷新してくれるだろう。
オド ウルラにはプール付きのブティックホテルも併設されており、オーベルジュとして利用することも可能だ。このレストランで1日3食食べて、1週間も滞在したら、心も身体も生まれ変わったようにリフレッシュされることだろう。
---fadeinPager---




---fadeinPager---

ワインの名産地として知られるウルラには10軒のワイナリーがあり、ヨーロッパのワイン好きの間では、それぞれのワイナリーを巡るウルラ・ワイン・ルートの旅が人気だ。そのうちの一つであるウルラ・ワイナリーで、ウルラ産ワインのテイスティングを愉しんだ。ここではカベルネ・ソーヴィニヨン、シラー、シャルドネといった人気品種はもちろん、ボアズケレ、カレシク・カラシ、ナリンジェ、ウルラ・カラス、フォチャ カラスといったローカル品種に加え、自社で開発したオリジナル品種のブドウも数多く栽培しており、トルコのワイン文化の奥深さを体感できる。





---fadeinPager---

夕食に訪れたのは、海辺のリゾート地アラチャトゥにあるオルタヤ・アラチャトゥ。日本でトルコ料理といえばケバブを中心とした肉料理の印象が強いが、実際に現地でローカルの食生活を目の当たりにしてみると、そのヘルシーさに驚くだろう。特に歴史的にもギリシャとの交流が深いエーゲ海沿岸のエリアでは、ギリシャ料理との共通点も数多く見つけることができる。何よりも魅力的なのは、前回のイスタンブール編でも紹介した前菜のメゼ。新鮮な野菜や豆、フルーツ、ヨーグルト、海藻類をふんだんに作った多種多様な前菜が、テーブルを埋め尽くしていく様子を見ているだけでも幸せになれるし、血糖値だって急降下していく気さえする。ただヘルシーなだけではなくて、それぞれに塩味、酸味、甘味、苦味、うま味の強弱があって、ちょっとずつ何種類も食べたくなる上に、ワインもパンも会話も止まらなくなる。しかも最近日本では価格が高騰しているオリーブオイルも、ウルラではどのレストランでも高品質でフレッシュで美味しいものが提供されるから、サラダ、肉類、魚介類、ヨーグルト、パンと、何にでも浴びせるように振り掛けたくなる。メゼは朝食、昼食、夕食問わず出てくるから、お酒と会話に夢中な時や、前の食事の量が多かった時などは、メゼだけで十二分に満足して、メインを頼まずに食事を終えることも多かった。

実際、6泊9日の取材旅行の間、毎朝ホテルの豪華な朝食で一日を始め、昼と夜はオドゥ ウルラのような星付きレストランやローカルレストランを巡りつつ、後先考えず盛大に食べて飲んで過ごして帰ってきたわけだが、帰国した日に恐る恐る乗ってみた体重計の数字は、なんと出国前と全く変わらなかったから驚きだ。もちろん○○kg痩せていた!と書いた方がよっぽど説得力があることはわかっているが、変わっていなかったのだからしようがない。しかし、毎食限界まで身体に詰め込んで、数時間したらまた目の前にあるものを食べ尽くすというような生活を1週間続けて、全く太らなかったということに、少なからず関心してもらえるのであれば嬉しい。