画家や写真家、デザイナーなど、クリエイターの生き方には、生涯をかけて追い求める独自の美学、かっこよさがあった。いまも輝き続ける国内外の8人を振り返る後編。
Pen最新号は『新時代の男たち』。ここ数年、あらゆるジャンルで多様化が進み、社会的・文化的にジェンダーフリーの概念も定着してきた。こんな時代にふさわしい男性像とは、どんなものだろうか。キーワードは、知性、柔軟性、挑戦心、軽やかさ、そして他者への優しさと行動力──。こんな時代だからこそ改めて考えてみたい、新時代の「かっこよさ」について。
『新時代の男たち』
Pen 2024年7月号 ¥880(税込)
Amazonでの購入はこちら
楽天での購入はこちら
---fadeinPager---
チャールズ・イームズ
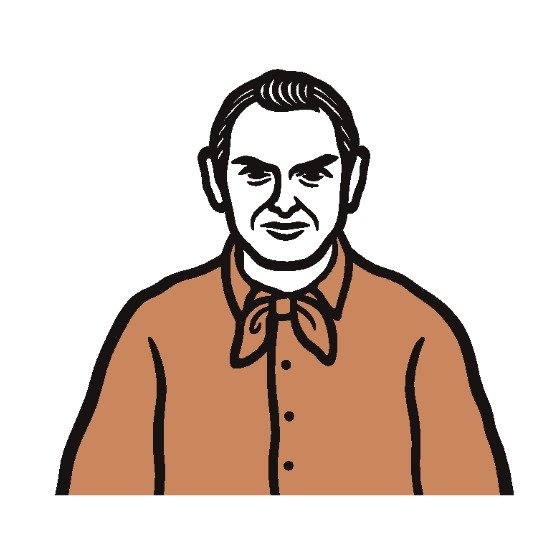
1907年生まれ。妻のレイ・イームズとともに、成型合板や繊維強化プラスチックといった新素材を取り入れたミッドセンチュリーデザインのアイコン的なプロダクトを次々に発表。20世紀のデザイン界を牽引し、後のデザイナーたちに大きな影響を与えた。 1978年逝去。
建築や家具のデザインだけでなく、映像やグラフィックなど幅広い分野において偉大なる功績を残したチャールズ・イームズ。ミッドセンチュリーモダンの草分け的な存在であったイームズが生み出したプロダクトは、素材の使い方や特徴的なフォルムを見れば見るほど、モノづくりに対する強いこだわりを感じることができる。しかも質がよく機能的なプロダクトづくりだけでなく、イームズは自らの手で製品カタログやポスターなどのデザインもすべて行っていたのである。
イームズの家具やプロダクトが半世紀以上経っても、ほぼオリジナルからかたちを変えずに生産され続けている事実は本当に凄いことだ。そもそも僕が家具に興味を持つきっかけをつくったのも、他でもないイームズによるプロダクトだったのだ。イームズの椅子に座るたびに、イームズ流の「Way of Life(生き方)」に思いを巡らしているくらいだ。
LAにあるイームズ・ハウスを訪れた時の思い出がある。広々としたリビングルームとダイニングには、ニューメキシコの古いカッチーナドールやメキシコや中南米の玩具、使い古した文房具、竹製の櫛などが、彼が生きていた当時のまま置かれていた。新しい技術や素材を取り入れて時代の先端を突き進んでいたイームズだったが、そこにプリミティブなものへのこだわりが活かされていたことに気づき、イームズにとってのホームとは、自分たちが心から愛したものとともに暮らす“実験の器”だったのだなぁと感じ入ってしまったのだ。
イサム・ノグチ

1904年生まれ。ブランクーシの助手をしながら彫刻を学び、後に魯山人から陶芸の手ほどきを受ける。1969年から香川県牟礼町(現、高松市)にアトリエを構えニューヨークと日本を往き来して彫刻、家具、陶芸、舞台美術、ランドスケープデザインなどを制作。1988年逝去。
そのイームズとも親交があったイサム・ノグチは、舞台芸術、空間デザイン、建築、庭園、陶芸など幅広い作品を生涯にわたって制作した。同時に家具や照明デザイナーとしてもマルチな才能を発揮したことでも知られている日系アメリカ人アーティストだ。
ノグチはニューヨークだけでなく鎌倉や香川にアトリエを持っていたが、来日するたびに京都の枯山水の庭園や、茶の湯の作法といった日本の伝統や文化を学んでいった。その上で「彫刻とはいったいなにか」を追求していき、たどり着いたのがノグチの代名詞ともいうべき自然石を使った彫刻だった。なかでも晩年に取り組んだ石彫は、ノグチ芸術の集大成というべきものだろう。石を彫り進めながら自分流のかたちにしていくことは、古くから東西の彫刻家たちの手法だったが、ノグチは自我の主張としてではなく、本来石が持っている「声」を聞きながら彫っていくやり方へと変わっていったのである。
「具現化できるものはすべて彫刻である」と考えたノグチは、家具のような実用品であっても、そのフォルムを彫刻的に追求し続けた。だから、そうやって生まれた家具やプロダクトには普遍性が備わっているのも確かに頷けるのだ。日系アメリカ人として生まれた境遇をバネにしながら、ノグチは自分の信念を貫きたぐいまれなる作品を残した。禅の精神や東洋的なニュアンスがある一方で、「外国育ちの僕」という自身の言葉からも感じられるように、日本人にはないボーダレスな感覚が流れているのもノグチ作品の面白さだろう。日米を行き来しながら途切れなく創造し続けたこの芸術家のあふれんばかりの創作魂には本当に憧れてしまう。
エドワード・ホッパー
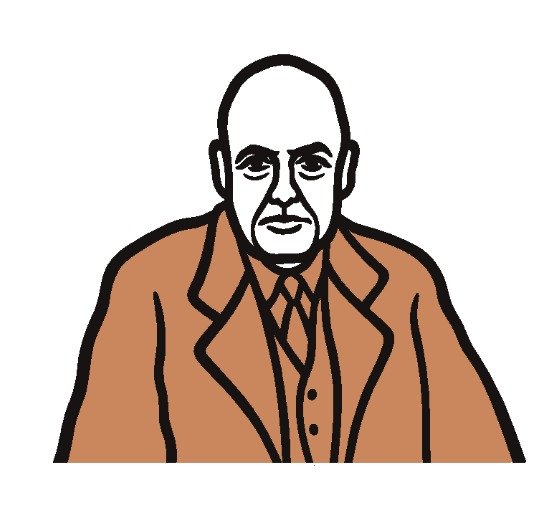
1882年生まれ。1920年代から60年代にかけて活躍したアメリカ絵画を代表する画家。ニューヨークの街路、オフィス、劇場、ガソリンスタンド、灯台、田舎の家など孤独な雰囲気が漂う人々、見慣れた都市や郊外の風景を単純化した構図で描いた。1967年逝去。
エドワード・ホッパーの『早朝の日曜日の朝』という作品を、自分が書いた『アートの入り口』の表紙にしたほど、僕は学生の頃からホッパーのことを崇拝してきた。コロナ禍の時も、部屋に一人で佇んでいる人物や人影のない風景を描いたホッパーの存在が再び大きくなっていき、彼の本や画集を読み漁っていた。
他のアメリカ人画家と同じく、若きホッパーもヨーロッパの影響を受けないアメリカ独自の芸術を生み出そうと試行錯誤していた。そしておもにニューヨーク市とニューイングランドの海岸沿いの小さな町を舞台にして、個人の陰鬱な生活、謎めいた静けさに包まれた人のいない風景をホッパーは描いた。近代的な建物は既にあったはずが、なぜかそういったものには興味を示さず、物思いに耽る人物や不穏な空気が感じられる場所をおもに描いたが、どの絵にも当時のアメリカという国の心理的側面が反映されていた。
ホッパーは身長195センチもある無口な大男で、風変わりで友人もほとんどいなく、自身の絵の登場人物のように静寂と孤独を好んだ。40歳を過ぎジョセフィンという伴侶を得ると、彼女は献身的にホッパー作品のモデルを務めるようになる。縫物をしたり、読書をしたり、煙草をふかしたり、ときには全裸になってホッパーの絵に七変化のごとく登場した。
ホッパーの絵には、時が過ぎ去ることへの寂寥や、孤独という感覚が息づいている。そのような孤独感は自分も含めて誰もが抱いているはずだが、そもそも孤独を感じることは、人が生きていくうえで必要なことではないか。そう思わせてくれるところが、僕がホッパーという画家により親近感を覚えてしまう本当の理由なのかもしれない。
ソール・ライター

1923年生まれ。1950年代からニューヨークにおいて第一線のファッション・カメラマンとして活躍するも、81年以降は商業写真から遠のき忘れ去られていく。2008年に出版された作品集により評価が高まり、日本でも展覧会が開催され人気を博した。2013年逝去。
孤独を愛し、不器用な生き方をしたのはソール・ライターも同じだろう。ライターは売れっ子の写真家として華々しく活躍していたが、なぜか表舞台から姿をぱったりと消してしまう。しかし80歳を過ぎた最晩年になって、50年代に撮ったカラー写真によって脚光を浴び、日本でも展覧会が何度も開催されセンセーションを起こした写真家である。
ライターは「写真を撮るのは自宅周辺だ。ミステリアスなことは意外にも身近で起きていると思っている。だから世界の果てまで行く必要もないんだ」と語っていた。その言葉通り、ライターの写真には誰もが目にしながらも、さほど気に留めないようなニューヨークの一瞬が、雨に濡れた窓越しや独特のフレーミングによって切り取られていた。
ライターは自身のさまざまな感情や心に残った印象を残すために、誰に見せるでもなく写真を撮り絵を描き続けた。そんなライターのパーソナルな写真が、半世紀を経て新鮮なものとして捉えられたのは、その特徴のある撮り方に加えて、彼が持って生まれた優れた色彩感覚にあったと考えられる。柔らかな色彩で知られるフランスの画家ピエール・ボナールや歌川広重、葛飾北斎の浮世絵からも影響を受けていたライターだが、その作品には彼の優しい眼差しと被写体への愛が感じられ、そのようなピュアな感性が時代を超えて見る者の心に響くのだろう。
ホッパーとライターは人知れず孤独に生きたかもしれない。しかし自分の気持ちに正直に生きた彼らは、人の心の深いところに訴えかけるなにか特別なものを残してくれたのである。
---fadeinPager---

『新時代の男たち』
Pen 2024年7月号 ¥880(税込)
Amazonでの購入はこちら
楽天での購入はこちら