画家や写真家、デザイナーなど、クリエイターの生き方には、生涯をかけて追い求める独自の美学、かっこよさがあった。いまも輝き続ける国内外の8人を振り返る。
Pen最新号は『新時代の男たち』。ここ数年、あらゆるジャンルで多様化が進み、社会的・文化的にジェンダーフリーの概念も定着してきた。こんな時代にふさわしい男性像とは、どんなものだろうか。キーワードは、知性、柔軟性、挑戦心、軽やかさ、そして他者への優しさと行動力──。こんな時代だからこそ改めて考えてみたい、新時代の「かっこよさ」について。
『新時代の男たち』
Pen 2024年7月号 ¥880(税込)
Amazonでの購入はこちら
楽天での購入はこちら
---fadeinPager---
伊丹十三

1933年生まれ。映画監督の伊丹万作の長男として京都市に生まれる。映画編集、商業デザイナーを経験後26歳で俳優デビュー。エッセイやテレビ、映像などの分野でも活躍。1984年に監督第一作『お葬式』を発表、10本の脚本監督作品を世に送り出した。 1997年逝去。
伊丹十三に興味を抱いたのは僕がまだアメリカに住んでいた頃だった。いまのような海外での空前のラーメン・ブームが起こるずっと前の80年代、伊丹が監督した『タンポポ』がニューヨークでも上映され、それまでの日本映画になかった瑞々しさが新鮮だった。その感動のまま第一作目の『お葬式』を観たのだが、題材もあいまってさらに驚かされた映画で、あんな問題作を世に送り出した伊丹十三という人に俄然興味を抱いてしまったのだ。
伊丹は映画監督だけにとどまらず、エッセイスト、雑誌編集長、テレビ番組制作者と稀代のメディア人である。僕が特に魅了されたのが彼の痛快なエッセイで、個性的なものの見方、独特の文体にぐいぐい惹き込まれてしまった。しかも彼の書くものはすべて自身の体験を通したものばかりで、検証に検証を重ねて書いていることが面白いほど伝わってきたのだ。
いまの世の中、ネット検索で手っ取り早く仕入れた知識を、ずっと前から知っていたかのように語るのが当たり前になっている。しかし伊丹は物事を徹底的に自分の目で見て、頭で考えさらに勉強して、実際にかたちにするまでに相当な元手と時間をかけていた。
「簡単に答えが出る人生なんかつまらない」と言わんばかりに、日頃から全力で考え、ルールに縛られず実にかっこよく生きた。そんな人こそ、いまの時代に本当に必要とされるのではないだろうか。
柚木沙弥郎
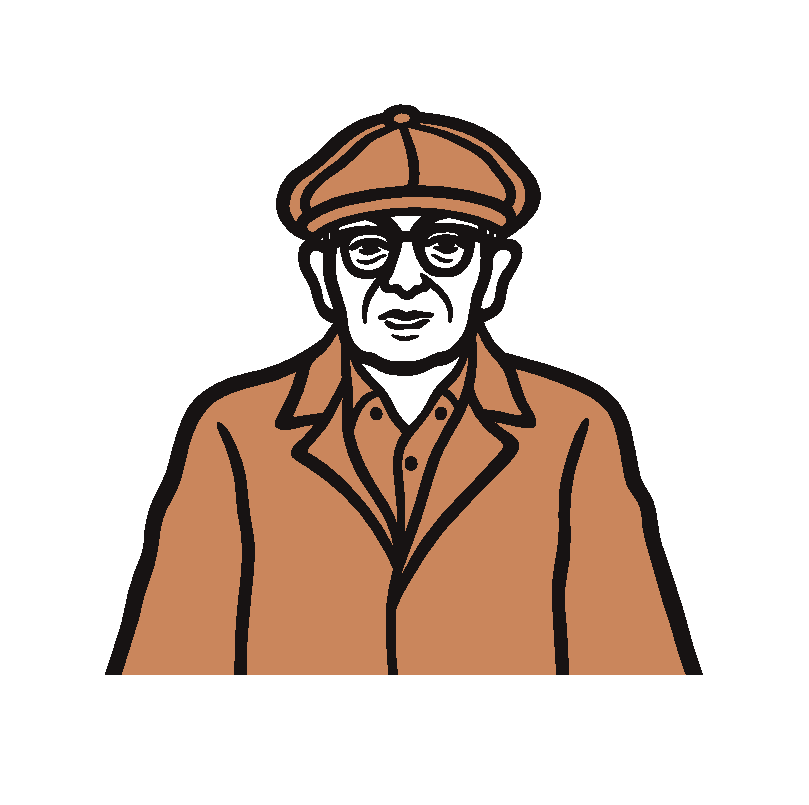
1922年生まれ。 民藝運動を知ったのち、芹沢銈介の作品に感銘を受けて染色家を志す。芹沢に弟子入り後、静岡県の正雪紺屋に住み込み、染色の技法を学ぶ。1972年に女子美術大学の教授、87年からは学長を務めた。染色のほか版画や人形、絵本などを制作。 2024年逝去。
布に型紙を直接当てて染める「型染め」の手法を用いて幾何学的な模様、ハサミなどの道具、人や鳥や動物、身近な自然から抽出した絵柄で知られるのが染色家の柚木沙弥郎だ。カラフルで遊び心が感じられる柚木の作品は、実に生き生きとしていて見るものを楽しい気分にさせてくれる。しかもそのあふれんばかりの豊かな感性は、102歳の晩年まで衰えることがなかったという。
柚木がインスピレーションの元としていたのが、中米や南米、日本の民芸品や玩具だった。素朴でユーモラスな彼の愛蔵品を見た瞬間、僕はハーマン・ミラー社でテキスタイルをデザインしていたアレキサンダー・ジラードが収集していた郷土玩具のことを思い出さずにはいられなかった。というのも、ふたりの収集していたものが驚くほど似通っていたからだ。調べたら、なんと柚木は64歳の時に米国のサンタフェを訪れ、ジラードが集めた玩具や民芸品に魅了されていたのだ。
実はその頃柚木は仕事に行き詰まりを感じ、染色をやめようとさえ思っていた。しかしジラードの郷土玩具やフォークアートや織物などを目にして、その素朴な造形に宿る遊び心に心が躍ってしまい、「ああ、なにをやってもいいんだ、でもどうせやるなら自分が楽しくないとつまらないな」と思い直し、それから再び染色に打ち込めるようになっていった。決まりごとにとらわれず、少年のような好奇心を持った柚木だからこそ人生の楽しみ方を教えてくれるのだろう。
小村雪岱

1887年生まれ。東京美術学校日本画科選科を卒業。1914 年に泉鏡花『日本橋』の装幀を手掛けて以来、鏡花のほとんどの本の装幀を任される。挿絵画家として邦枝完二の新聞連載小説『おせん』で人気を博す。歌舞伎などの舞台美術家としても活躍した。 1940年逝去。
「OSAMU GOODS」の生みの親として知られるイラストレーターの原田治の著書『ぼくの美術帖』で小村雪岱のことを知った。原田は雪岱のことを「選んだ絵の様式美が古典的であるだけでなく、画家として歩んだ道も古典的と云える。しかもその流れの中では、実に新しい仕事をしていた」と評しているが、ちょうど僕も当時行われていた雪岱の展覧会の作品に魅了され、その粋な人柄にも心を奪われてしまったのだ。
雪岱の作品は原田が言うように一見すると古典的だが、ハッとさせるような新鮮な感覚が息づいている。たとえば、柳が垂れる縁側奥の畳間に三味線と鼓がポツンと置かれている『青柳』という作品は、人を描かずとも人の気配が感じられ、不思議な静寂さと時の流れが感じられるというものだ。余白と静謐とが絶妙に調和したようなその作風は、どこか現代のグラフィックデザインにも通じる空気感があり、そのような懐の深い作品を見て僕は一目で雪岱のファンになってしまったというわけだ。
文芸や演劇に耽溺していた雪岱は本の装幀、小説の挿絵、舞台装置や舞台衣装を専門としていた。本絵(ほんえ)と呼ばれた絵画や版画が比較的少なかったため、日本画壇の範疇で語られることの少ない絵師であった。しかし彼の活動は画家と呼ぶには収まりきれないものだったし、デザイン的要素を組み合わせた独創的な作品はもっと評価されて然るべきだ。江戸の粋をモダンに生まれ変わらせた“意匠の天才”雪岱は、小津安二郎の昭和モダニズムにつながる人なのだ。
倉俣史朗

1934年生まれ。1965年に自身の事務所を構え、驚きに満ちた家具や店舗デザインを手掛ける。80年代はイタリアのデザイン運動「メンフィス」に参加。イッセイ ミヤケの海外の店舗デザインによってその名が世界中に浸透したが91年に56歳で逝去した。 1991年逝去。
1991年に56歳で亡くなった倉俣史朗は、日本だけでなく海外で高く評価されているデザイナーである。代表作として名高い『ミス・ブランチ』は、液体アクリル樹脂の中に赤いバラの造花を流し込んでつくられた驚きの椅子であり、その繊細な造形美には誰もが心が奪われてしまうはずだ。他にも透明の板ガラスだけで組まれた『硝子の椅子』というのがあり、座っていいものかと躊躇してしまうほど緊張感に満ちた作品だ。
そんな倉俣の家具デザインに共通するのは、重力から解放されたような浮遊感、夢心地という感覚だ。倉俣はデザインする際、夢からインスピレーションを受けていたというが、“儚さ”という日本人的な感性が息づいているのも好きなところだ。「使うことを目的としない家具、ただ結果として家具であるような家具に興味を持っている」とも語っていたが、そこにアート的な感覚があるのは、機能性や見た目の形状に主眼を置いていなかったからだろう。腕利きの職人たちとつくった奇跡のようなプロダクトを見るにつけ、彼がいかに戦後の日本デザイン界を牽引したレジェンドだったかを心から納得してしまうのだ。
---fadeinPager---

『新時代の男たち』
Pen 2024年7月号 ¥880(税込)
Amazonでの購入はこちら
楽天での購入はこちら