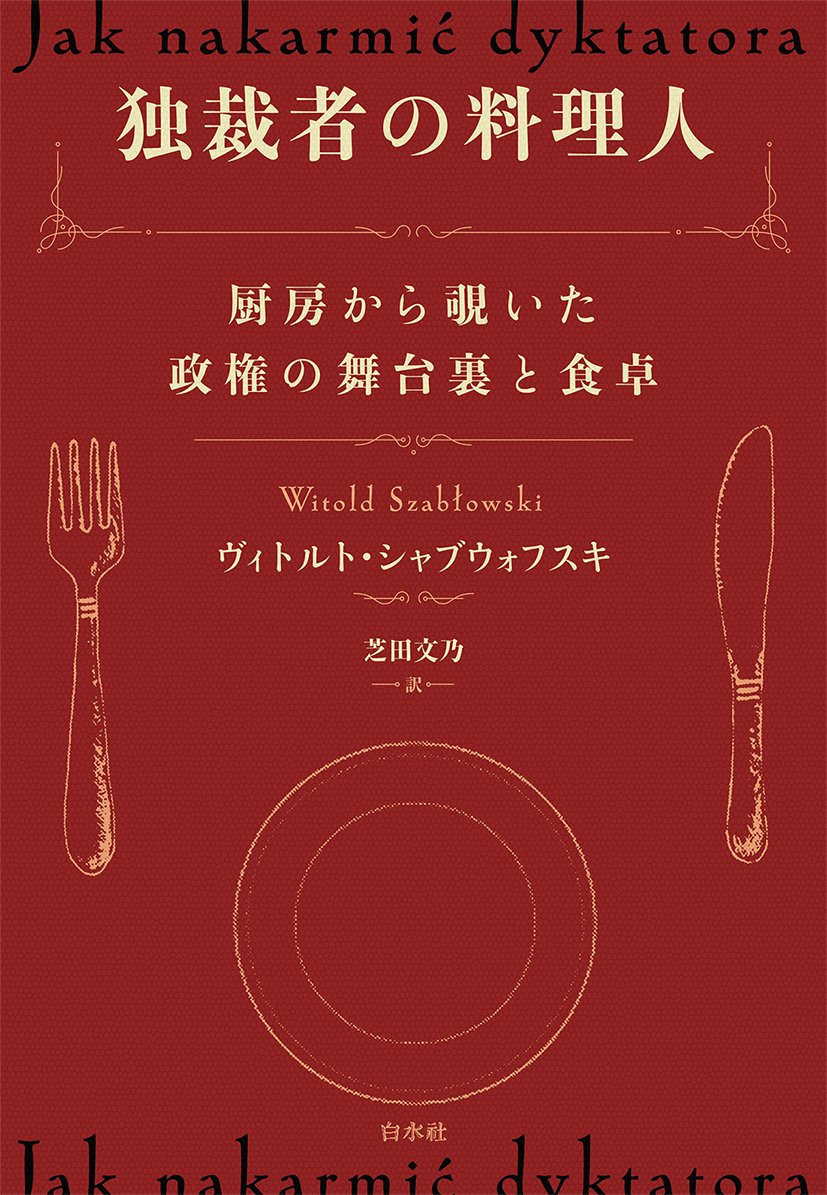【Penが選んだ、今月の読むべき1冊】
『独裁者の料理人 厨房から覗いた政権の舞台裏と食卓』
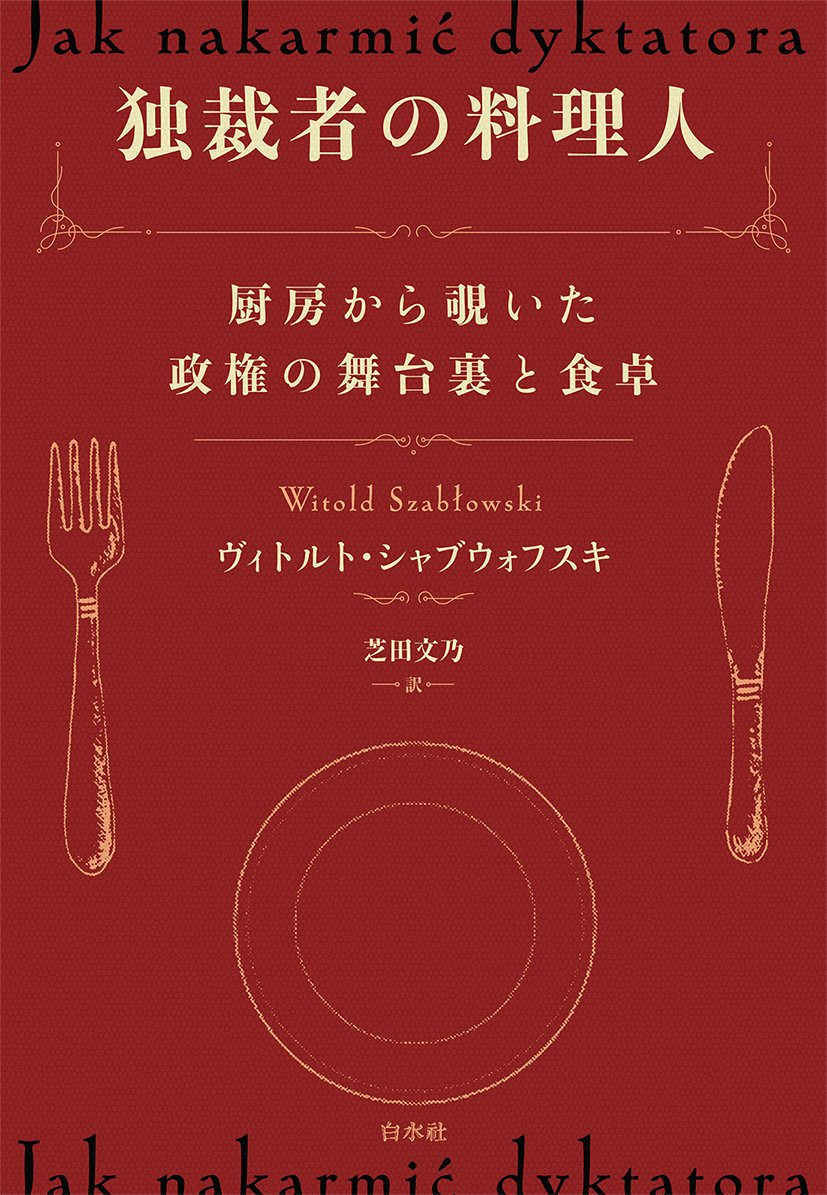
牛肉と羊肉を半々に混ぜて挽き、トマト、玉ネギ、パセリと混ぜたら、串の上に薄く広げ、グリルにのせて焼く。ピタでくるめば、コフタの出来上がり。しかし、その日のコフタはおかしかった。口の中が焼けるように熱い。「毒か?」アブー・アリはぞっとした。「誰かがサダムを毒殺しようとして、私はそれを食べてしまったのか⁉」
彼はサダム・フセインのお抱え料理人。異変の理由は、サダムが誰かからもらったタバスコを試してみたせいだった。「もしも自分がこんなふうに肉を駄目にしたら、大統領は私の尻を蹴って、金を返せと命じたはずだ」。思わずそう口走ると、すぐさまサダムに呼ばれた。「私のコフタが口に合わなかったそうだな」。殺される。独裁者の料理人は、常に死と隣り合わせなのだ。
人が誰も食べなければ生きていけない以上、厨房は歴史の舞台裏が最もよく見える場所だ。本書にはカストロやポル・ポトの料理人も登場する。歴史の生き証人である彼らが自ら語り手となるのだから、面白くないはずがない。アミンが軍事クーデターを起こした時も、宮廷の料理人たちは淡水魚のティラピアと山羊肉のピラフを用意した。なぜならそれがアミンの好物だと憶えていたから。料理を気に入ってもらえれば殺されずに済む。料理は、窮地で生き残るためのサバイバル術でもあるのだ。
ポル・ポトの料理人はいまだに彼を崇拝していた。洗脳と憐れむのはあまりに短絡的だろう。独裁者が生まれる背景には飢えがある。チェ・ゲバラは黒インゲン豆が大好物だった。歴史的な瞬間に彼らがなにを食べていたかを知りたければ、この本にはそのレシピも載っている。なにより一庶民に過ぎなかった料理人たちが先の見えない時代をどう生き抜いたのかに惹き込まれずにはいられない。
※この記事はPen 2023年7号より再編集した記事です。