仕事を忘れ、じっくりと読書に浸れる年末年始。今こそ読むべき名作としてお薦めしたい5作をピックアップした。
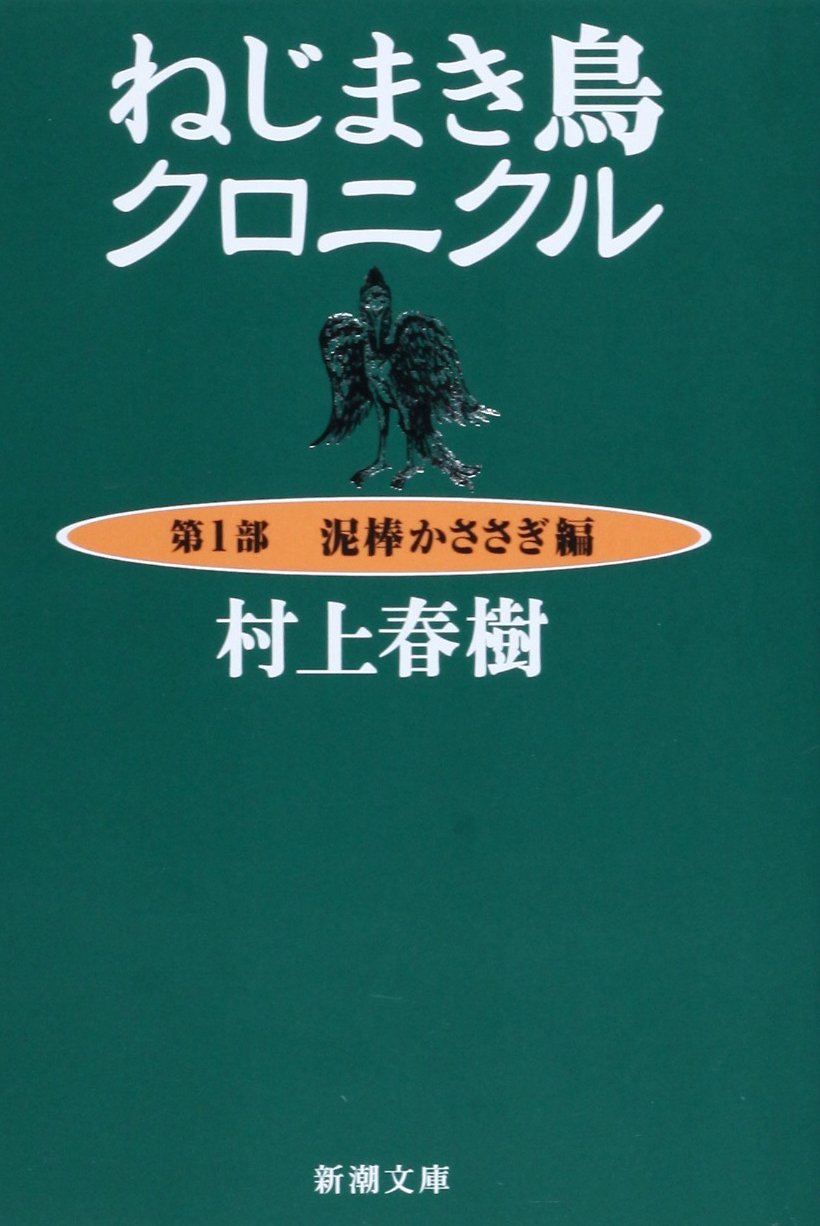
村上春樹『ねじまき鳥クロニクル』
大英博物館から徒歩数分のところにロンドン大学のSOAS(School of Oriental and African Studies)がある。アジアやアフリカに関する世界最大級の研究機関だ。私が村上春樹さんの大著『ねじまき鳥クロニクル』に出会ったのは、同校が蒐集する約130万冊に及ぶアジア、アフリカ関連コレクションとしてだった。
20年ほど前にSOASに語学遊学(文字通り遊んでばかりだった)した当初、私は日本人作家の小説をほとんど読んだことがなかった。日本語で読むものと言えば研究書や海外のミステリーの翻訳書が中心だったし、せっかくイギリスにいるのだからと英語の本ばかりを読んでいた。しかし英語で暮らす生活を億劫に感じて、日本語で読めるものはないか、と図書館をさまよっていたら村上作品が何冊か並ぶ書棚を見つけたのだ。
以来私は「村上主義者」となり、小説はほぼ全て読んでいる。しかも何回も。中でも心が荒んできたと自分で思うとき、禊のような意味で手に取るのがこの本だ。
以前、同期の編集者が、村上さんの作品が「面白いけどはっきり言って意味わからん」と話していたのを覚えている。確かに彼の小説は、文章こそ読みやすいが、内容的には理解しやすい類のものではない。そこには常に「理解しがたい何か」が潜んでいる。いやむしろ、理解できない事に意味があるように感じられる。
近所に住む女の子・笠原メイから「ねじまき鳥さん」と呼ばれる主人公「僕=岡田トオル」は、仕事で多忙な妻に代わって家事をしながら新しい職を探している。しかしある時、妻が家に戻らなくなり、「僕」はその理由に全く思い当たらない。そして出て行った妻について思いを巡らす時、果たして自分は彼女のことを本当の意味でどれだけ知っているのだろう、と自問する。
“ひとりの人間が、他の人間について十全に理解するというのは果して可能なことなのだろうか。つまり、誰かのことを知ろうと長い時間をかけて、真剣に努力をかさねて、その結果我々はその相手の本質にどの程度まで近づくことができるのだろうか。”
明示はされないが、そこには既に答えがある。つまり人は他者を完全には理解することが出来ない、ということだ。しかし村上さんも「僕」も、諦めない。他者の理解不可能性をいわば前提として、それでも理解する努力を続けているように思う。
私のメインの仕事は「神」という理解できない存在と向き合うことだ。神を十全に理解できるなどと言う同業者がいたら会ってみたいものだ。多分、宗教が現代社会に役立つとすれば、それは理解不可能な他者と対峙する心構えを、同じく理解不可能な存在との対話から見出せることにあるのではないだろうか。
神は言葉を発することなく、我々人間のほうが、進んでその意図を推し量らねばならない。他人もまた、本当の意味で胸の内をさらけ出すことはない。人と人との理解はいつまでも百パーセントに達することはない。だけど少なくとも一歩ずつ、理解へと近づいていくことは出来る。私が本作から学び、そして折に触れて立ち返るのは「不可知と向き合う作法」とでもいうべきものだ。
今は神社が一年で一番忙しい年末~正月。それでも3部作を手に取って何度でも読み返したくなる魅力がこの本にはある。(常陸国総社宮 禰宜/東京外国語大学特別研究員/ライター 石﨑貴比古)
---fadeinPager---
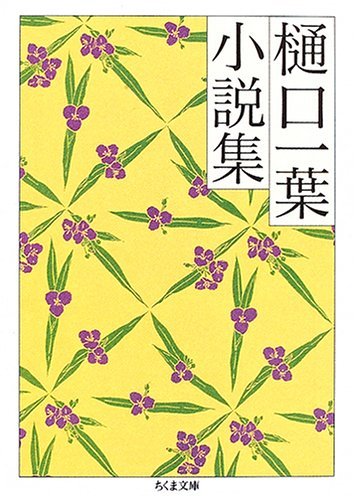
樋口一葉『にごりえ』
2022年に生誕150年を迎える樋口一葉(1872~1896)は、24歳6ヵ月という短い生涯ながら名作の数々を生み出した。一葉の作品はほとんど古典となりつつあるが、そこに描かれた家族制度や女性差別、貧困といった厳しい現実に翻弄される女性たちの姿は、現代社会に通じるものがある。「にごりえ」も、私娼・お力の苦悩と悲劇を描く中で人間存在の深淵に迫る、普遍的なテーマを持った作品だ。
物語の舞台は、東京・小石川柳町辺りの、田圃を埋め立て新たに開発された「新開地」。一帯には、飲食店を装いながら密かに私娼を置く銘酒屋が建ち並んでおり、お力はその一軒である「菊の井」の一枚看板だった。彼女は上客の結城朝之助(ゆうきとものすけ)と親しくなるも、自分の素性を明かそうとはしない。また、客の一人・元蒲団屋の源七は、妻子がありながらお力に入れあげ、今は店もつぶして落ちぶれたが、なおお力に強い未練を残していた。
盆の夜、お力は衝動的に店を飛び出し、横町の闇の中で独白する。「あゝ嫌だ嫌だ嫌だ、何うしたなら人の声も聞えない物の音もしない、静かな、静かな、自分の心も何もぼうつとして物思ひのない処へ行かれるであらう」「これが一生か、一生がこれか」―。実は彼女は祖父、父ともに悲惨な人生を送り、自身も貧しく生まれ育った。「此様な宿世で、何うしたからとて人並みでは無いに相違な」いと、私娼をやめることも、「奥様」になることもできない。やがてお力は朝之助にこうした自分の素性を話す。一方、源七夫妻はお力が息子に買い与えた菓子をきっかけに、諍いを起こして……。
「にごりえ」は1895年9月、文芸誌「文芸倶楽部」に掲載。当時、一葉が暮らした本郷区丸山福山町の家の近くに銘酒屋があり、そこで働く女性たちとの交流から生まれた作品といわれている。その心理描写は発表当時から評価され、特にお力の独白の場面は時を経ても変わらず読者に強い印象を与える。自身も社会の矛盾に苦しんだ一葉の実感も込められているであろう、お力の心の叫びにぜひ耳を傾けてみてほしい。
一葉の作品は雅俗折衷体と呼ばれる、文語体と口語体を混合した文体で書かれており、一見すると馴染みにくいと感じるかもしれない。その場合は、声に出して読む、あるいは朗読を聞くのがおすすめ。一葉の文体には独特のリズムがあり、「耳から入ると理解しやすい」ともいわれている。また、「にごりえ」は現代語訳も出されており、そうした書籍を手に取ってみても作品の味わい方が広がるかもしれない。(神奈川近代文学館 本田未来)
---fadeinPager---
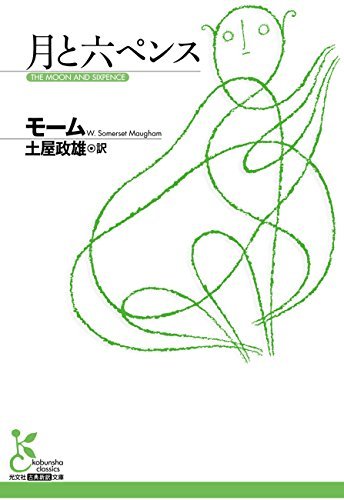
サマセット・モーム『月と六ペンス』
『月と六ペンス』は、イギリスの人気作家、サマセット・モームが、画家ポール・ゴーギャンに着想を得て書いた小説で、1919年に発売するとイギリスとアメリカで大ベストセラーとなった。
主人公のストリックランドはあくまで創作上の人物だ。だが読んでいるとどうしてもゴーギャンとその作品を思い浮かべてしまう。主人公が実在の画家のように思えるほど、人間の業(ごう)を生々しく描いているのだ。
ストリックランドは、40歳で絵を描くためロンドンに妻子を置いて、パリへと向かった。株式仲買人としてよく働き、よき家庭人として振る舞っていた男が、いきなりこれからの人生は絵を描いて生きていく、と決めたのだ。妻は、きっと若い女にたぶらかされて出奔したのだと思い込むが、そうではなかった。彼はたったひとりで金も持たずに一歩を踏み出す。
これからの人生は、絵を描くことに費やしたい。その想いだけで突っ走るストリックランドだが、ここで描かれているのは、夢を追い求める崇高な姿ではない。そこがモームの巧みさで、ストリックランドは傍若無人なのに魅力的だ。
妻子を置いて出てきたことを責められても「不幸など、いずれ乗り越える」と平然としている。冷徹なのではない。実際のところ、しばらくすると妻は自分の境遇を理解し、周囲の同情を集めながら見事に自活するようになる。人間はしたたかにできていることをストリックランドはよくわかっていた。
自分に対してもそうだ。どんなに困窮しても彼は自身の選択を後悔したりしない。絵を描く以外は、のらりくらりと生きていく。他人の評価にも興味がなく、絵を売ることもなかった。だから「自分には絵の才能があるのか」「この先、絵で食っていけるようになるのか」と思い悩むこともない。芸術家に必要なのは、自分を信じる力なのだということがよくわかる。彼が偉大な画家として評価されるようになったのは、死後のことだ。
タイトルの『月と六ペンス』は、あなたは月と六ペンス、どちらに価値を見出すのかと問われているように思う。ささやかな幸せを手に入れたいのか、それとも手が届かないものを追い求める覚悟があるのか。
ストリックランドが、マルセイユを経由してタヒチに渡ったのは47歳のときだった。40歳からの人生を、絵を描くことに捧げた男が最後に行き着いたのは、楽園だったのか。(ライター 今泉愛子)
---fadeinPager---
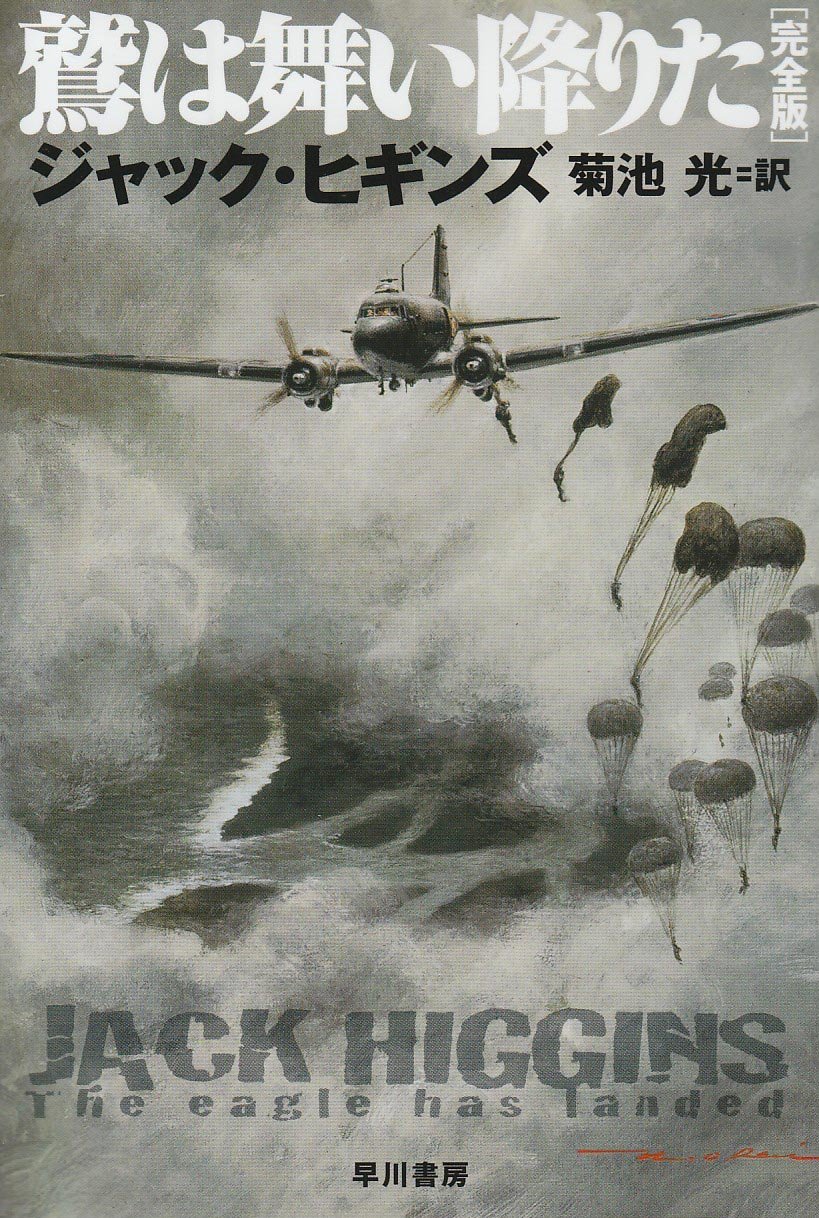
ジャック・ヒギンス『鷲は舞い降りた』
最近は老眼が進んでなかなか本を手に取ることが少なくなってしまったが、昔は活字中毒と思うほど、本をたくさん読んだ。特に好きだったのが冒険小説というジャンル。日本冒険小説協会の会長だった故内藤陳氏が薦めた作品はほとんど読んだ記憶がある。今でも時々手にして再読するのが、英国の冒険小説の大物、内藤氏が神と崇めるジャック・ヒギンスが1975年に発表した『鷲は舞い降りた』という作品だ。
英国北部のノーフォークにある田舎町を訪れた作家ジャック・ヒギンスは教会で隠されていた墓石を発見する。そこには<1943年11月6日に戦死せるクルト・シュタイナ中佐ドイツ落下傘部隊13名、ここに眠る>との墓碑銘が刻まれていた。こんな冒頭で始まる。
舞台は1943年、敗戦迫る第二次世界大戦中のドイツ、そして英国。山中に幽閉されていてイタリア首相ムッソリーニの特殊部隊による救出に狂喜したナチスの総統ヒットラーは起死回生のミッションを思いつく。英国の宿敵、ウィンストン・チャーチルを誘拐するという突拍子もない企てだ。当初、この作戦は実現不可能を思われていたが、田舎町スタドリ・コンスタブルに潜むスパイから村から近い宿でチャーチルが休暇を過ごす予定があるという情報が打電され、ゲシュタポ長官のヒムラーはその町に落下傘部隊を送り、チャーチルを拉致することを命じる。その隊長に指名されたのが、クルト・シュタイナ中佐。ヒムラーは彼のことを「彼以上に勇気ある男は、まずいないだろう。非常に頭が良くて、勇気があって、冷静で、卓越した軍人──そしてロマンチックな愚か者だ」と評する。シュタイナはドイツ軍人の父とアメリカ人の母を持ち、ロンドンとパリで教育を受け、英語はイギリス人と変わらないほど達者だった。軍人となってからは落下傘部隊の英雄にまで登りつめるが、ユダヤ人少女を救ったことが反逆行為とみなされ、処刑は免れたものの、自殺的な任務に就いていた。それもあってヒムラーは「ロマンチックな愚か者」と言ったのかもしれない。
当初このミッションに懐疑的であったシュタイナだったが、責任者ラードル中佐の説得を受け入れ、チャーチルが休養を取る村の近くの海岸に落下傘で降下する。これこそ、鷲は舞い降りた。連合国側のポーランド義勇軍を装い、先に潜入していたIRA=アイルランド共和国の活動家、リーアム・デブリンの手引きでスタドリ・コンスタブルに部隊の演習という名目で潜入することに成功する。
作者自らが登場する意外な書き出しから、英国への潜入、チャーチルとの対決へと、まるで映画を観ているかのようにテンポ良く物語は進む。果たして、彼らはチャーチル首相の誘拐に成功するのか……。
ちなみにこの作品は、『荒野の七人』(1960年)や『大脱走』(1963年)で知られる監督ジョン・スタージェスの手で1976年に映画化されている。タイトルは『鷲は舞いおりた』。主人公のシュタイナをマイケル・ケイン、IRAの闘士デブリンをドナルド・サザーランドが演じるが、小説とほとんど同じ筋立て。さらに同じシュタイナとデブリンのその後の活躍を描いた『鷲は飛び立った』という続編もある。こちらもオススメだ。(編集者/ライター 小暮昌弘)
---fadeinPager---
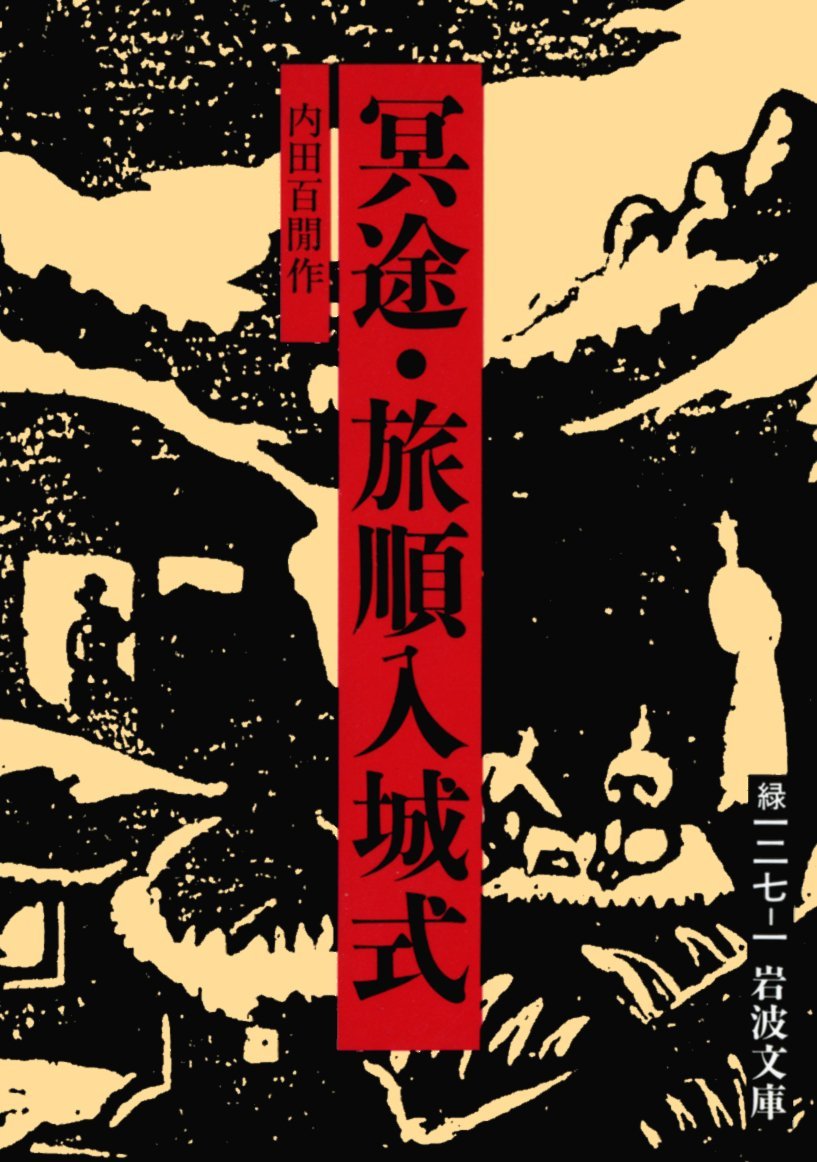
内田百閒『冥途』
芥川龍之介はこの作品を次のように評した。
漱石先生の『夢十夜』のように、夢に仮托した話ではない。見た儘に書いた夢の話である。(中略)作者が文壇の塵氛(じんぶん)の中に、我々同様呼吸していたら、到底あんな夢の話は書かなかったろうと云う気がする。書いてもあんな具合には出来なかろうと云う気がする。つまり僕にはあの小品が、現在の文壇の流行なぞに、囚われて居らぬ所が面白いのである。(「文芸時報」第42号、昭和2年8月4日)
夏目漱石に師事し、『百鬼園随筆』などの随筆集や、鉄道に乗ることを目的に鉄道旅をする紀行文『阿房列車』などで新境地を切り開いた小説家で随筆家の内田百閒。「こんな夢を見た」で始まる10篇の夢物語を描いた『夢十夜』の影響を受けながらも、若くして確立した文学表現で異界との境界があやふやな幻想譚を描いた文壇デビュー作が『冥途』だ。
「冥途」「山東京伝」「花火」「件」「土手」「豹」という、3ページほどの6本の短編が「新小説」大正10年1月号に掲載されたのだが、1本目の「冥途」から、異界の入口に触れる映画の一場面に引き込まれる感覚を与えてくれる。舞台は長い土手の下の「一ぜんめし屋」。定食屋のような店だ。主人公の「私」が店の卓に腰掛けていると、隣では4〜5人連れの客が食事をしていて会話が聞こえてくる。どうやら自分のことを話しているようだ。腹が立つ。しかしひとりの男の声が聞こえてくると、「私は俄(にわか)にほろりとして来て、涙が流れた。何と云う事もなく、ただ、今の自分が悲しくて堪らない」。
その声の主が誰なのか、わかるようでわからない。土手がキーワードとなる。土手の向こうの下には川が流れているのだろう。つまり、そこが冥途と浮世の境目だ。声に耳を傾け、話す姿を見ようとするもその姿はぼんやりとして判然としない。話す内容も聞こえてきたり聞こえなかったり。「私」の感情は揺さぶられる。
1匹の蜂が見え、その男の声が「はっきりして来るにつれて、私は何とも知れずなつかしさに堪えられなくなった」。男が蜂のことを話し始めると、その描写が自分の子供の頃の記憶と一致するのだ。そう、その男は自分の父親だったのだ。土手の向こうから飯を食いに来たのだろうか。「私」が「お父様」と声をかけても通じず、異界とのコミュニケーションが不可能なことを突きつけられるような場面から「冥途」は終盤に向かう。
「見た儘に書いた夢の話」だと思わせる不条理がこの作品には横たわっており、夢のやるせなさが読者の感情を揺さぶってくる。そして言葉のテンポが心地よく、走馬灯を追いかけるように文字を追いかけたくなる。文学は必ずしも筋を追う必要がなければ、登場人物の背景や感情を分析する必要もない。言葉の連なりから光景を思い浮かべ、その情景に自分の感情を投影できるのがひとつの名作文学の姿ではないか。内田百閒が綴った33篇の夢物語に身を委ねれば、心地よく幻想へと誘ってくれるはずだ。(編集者/ライター 中島良平)